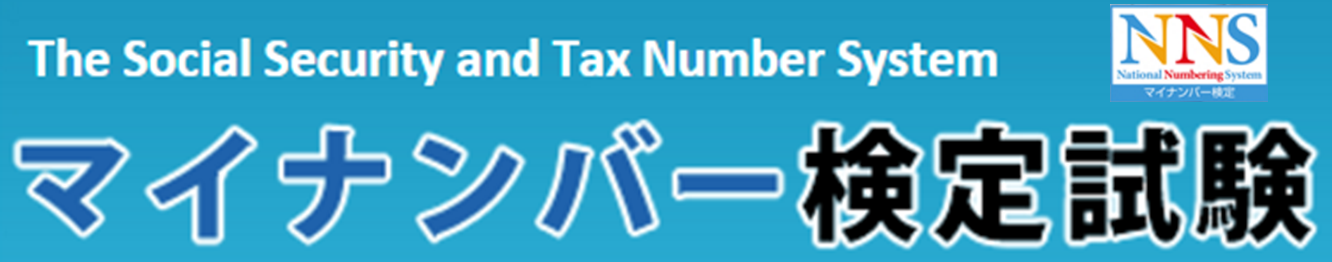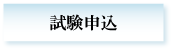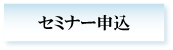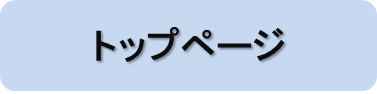
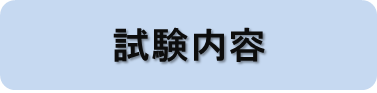
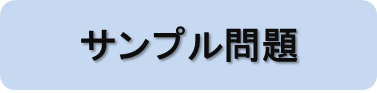
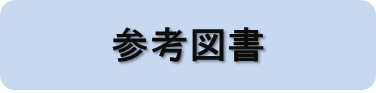
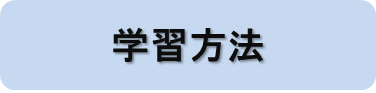
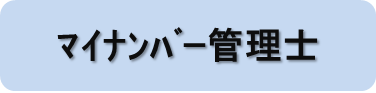
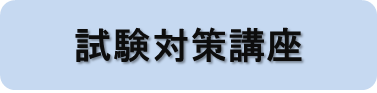
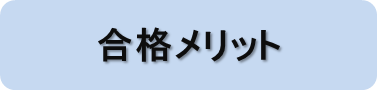
マイナンバー実務検定1級または2級の合格者は、「個人情報保護士認定試験」を
受験する際に『課題Ⅰのマイナンバー法の理解』が免除となります。
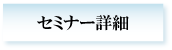
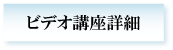
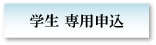
学生の方は学割が適用されます。
受験の際に学生証の提示が必要となります。
マイナンバー実務検定
1級・2級出題範囲
注1:ここでは「番号法」と表記していますが、「マイナンバー法」とも呼ばれる場合もあります。正式な法律名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。
注2:番号法及びその関係法令については、施行されていない部分も出題範囲に含まれるものとします。
注3:何級からでも受験できます。
注4:1級は以下の2つのガイドラインも出題内容に含み、2つのガイドラインから各々5~10問程度出題される見込みです。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)
金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
 | 番号法の背景・概要 | 番号法成立の経緯・背景、番号法の成立と施行 |
|---|---|---|
| 番号法のメリット、今後の課題・留意点など | ||
| 第1章(総則) | 法の目的(1条) | |
| 定義(2条) | ||
| 個人番号、個人番号カード、個人情報、特定個人情報、個人情報ファイル、特定個人情報ファイル、本人、行政機関、個人番号利用事務、情報提供ネットワークシステム、法人番号、など | ||
| 基本理念(3条) | ||
| 国の責務(4条) | ||
| 地方公共団体の責務(5条) | ||
| 事業者の努力(6条) | ||
| 第2章(個人番号) | 個人番号の指定及び通知(7条) | |
| 個人番号とすべき番号の生成(8条) | ||
| 個人番号の利用範囲(9条) | ||
| 再委託(10条) | ||
| 委託先の監督(11条) | ||
| 個人番号利用事務実施者等の責務(12条・13条) | ||
| 個人番号の提供の要求(14条) | ||
| 個人番号の提供の求めの制限(15条) | ||
| 個人番号の本人確認の措置(16条) | ||
| 第3章(個人番号カード) | 個人番号カードの交付等(17条) | |
| 個人番号カードの利用(18条) | ||
| 第4章 第1節 (特定個人情報の提供の制限等) | 特定個人情報の提供の制限(19条) | |
| 特定個人情報の収集等の制限(20条) | ||
| 第4章 第2節 (情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供) | 情報提供ネットワークシステム(21条) | |
| 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(22条) | ||
| 情報提供ネットワークシステムにおける情報提供等の記録(23条) | ||
| 情報提供ネットワークシステムにおける秘密の管理(24条) | ||
| 情報提供ネットワークシステムにおける秘密保持義務(25条) | ||
| 第5章(特定個人情報の保護) | 特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針(26条) | |
| 特定個人情報保護評価(27条) | ||
| 特定個人情報ファイルの作成の制限(28条) | ||
| 行政機関個人情報保護法等の特例(29条) | ||
| 情報提供等の記録についての特例(30条) | ||
| 地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護(31条) | ||
| 個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者が保有する特定個人情報の保護(32条~35条) | ||
| 第6章(特定個人情報保護委員会) | 特定個人情報保護委員会の組織(36条~49条) | |
| 特定個人情報保護委員会の業務(50条~56条) | ||
| 特定個人情報保護委員会規則(57条) | ||
| 第7章(法人番号) | 法人番号(58条~61条) | |
| 第8章(雑則) | 雑則(62条~66条) | |
| 第9章(罰則) | 罰則(67条~77条) | |
| 附則 | 附則 | |
| 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン | 条文に関連する箇所が出題範囲となります。 | |
| 関連法令等 ※番号法に関連する箇所、基本的な部分が出題範囲となります。 | 施行令、施行規則、行政機関個人情報保護法、個人情報保護法、特定個人情報保護評価に関する規則、特定個人情報保護評価指針、住民基本台帳法、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(行政手続IT利用法)、地方公共団体情報システム機構法など |
試験形態:マークシート方式
試験時間:1級…120分/2級…90分
問題数:1級…80問/2級…60問
合格点:1級・2級…80%以上
マイナンバー実務検定3級 出題範囲
注1:ここでは「番号法」と表記していますが、「マイナンバー法」とも呼ばれる場合もあります。正式な法律名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。
注2:出題の順番、内容等は変更となる場合がございます。
注3:何級からでも受験できます。
 | 番号法成立の経緯・背景 | 番号法成立の経緯・背景 |
|---|---|---|
| 番号法の成立と施行 | ||
| 番号法の今後の課題や留意点 | ||
| 番号法の概要 | 番号制度の仕組み | |
| 個人番号・法人番号に対する保護 | ||
| 個人と番号法 | 個人番号の通知(通知カード)、個人番号カード | |
| 情報ネットワークシステム、マイ・ポータル | ||
| 個人番号を利用する場面や取扱いの際の遵守事項など | ||
| 民間企業と番号法 | 民間企業にとっての番号法 | |
| 個人番号や法人番号を利用する場面や取扱いの際の遵守事項など | ||
| 地方公共団体・行政機関・独立行政法人等と番号法 | 地方公共団体・行政機関・独立行政法人等にとっての番号法 | |
| 個人番号や法人番号を利用する場面や取扱いの際の遵守事項など | ||
| 特定個人情報について | ||
| 番号法のこれから | 番号法制度の活用と今後の展開 | |
| 罰則 | 罰則 | |
| 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン | 条文に関連する箇所が出題範囲となります。 | |
| 関連法令等 | 施行令、施行規則、個人情報保護法など、番号法に関連する箇所、基本的な部分が出題範囲となります。 |
試験形態:マークシート方式
試験時間:3級…60分
問題数:3級…50問
合格点:3級…80%以上(平成28年6月実施より)
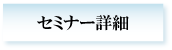
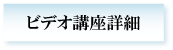
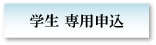
学生の方は学割が適用されます。
受験の際に学生証の提示が必要となります。