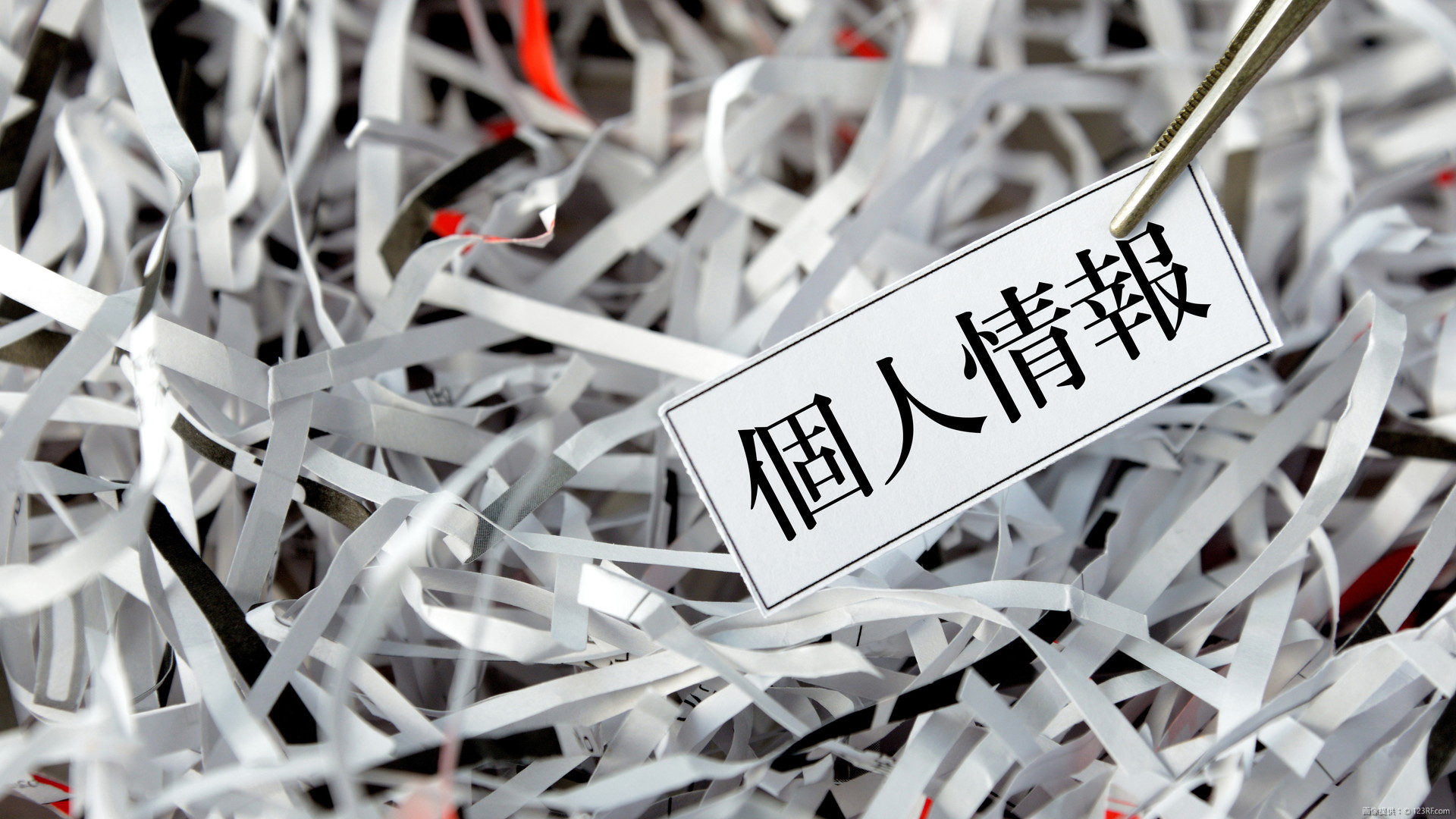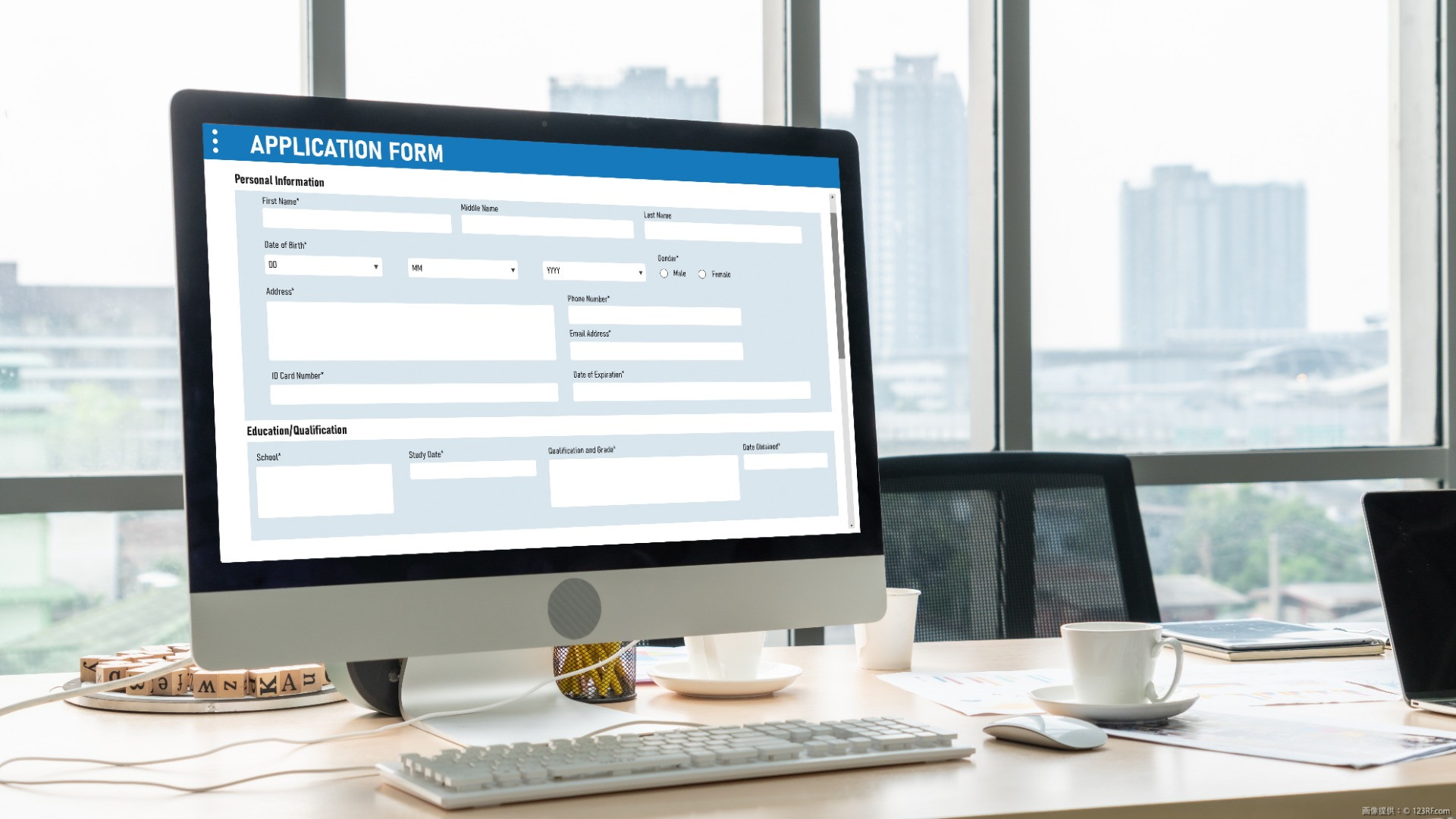個人データの共同利用について解説!過去に取得した個人情報を共同利用するときの注意点も
2025.1.10

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人データの共同利用について解説!過去に取得した個人情報を共同利用するときの注意点も
企業活動のグローバル化やデジタル化が進むなか、個人情報の取り扱いがますます重要視されています。とくに、グループ企業間での個人データの共同利用については、法令遵守と効率的な事業運営の双方が求められます。そこで今回は、個人データの共同利用に関する考え方から実務上の注意点まで詳しく解説します。

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人データの共同利用とは?


個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人データの共同利用は、データを提供する際の煩雑な手続きを省略し、円滑な情報活用を図るための制度として法律で認められています。複数の事業者間でデータを共有し、効率的な業務運営を実現する仕組みです。
企業グループ内での情報共有ニーズの高まりを背景に、本制度が広く活用されています。各社が保有するデータを適切に活用することで、顧客へのサービス品質向上や業務の効率化を実現するためです。たとえば、大手小売チェーンでは、実店舗とECサイト間で購買履歴や会員情報を連携させ、一貫性のあるサービスを提供しています。また、店頭で気に入った商品をオンラインで再注文したり、ポイントを相互に利用したりと、顧客の利便性を高めているのが現状です。
一方、金融グループでは、銀行・証券・保険各社の間でデータを連携し、総合的な資産運用サービスを展開しています。
このように、事業者間でのデータ活用は、顧客満足度の向上と業務の効率化に貢献する重要な取り組みといえます。ただし、その実施にあたっては法令で定められた要件を遵守し、適切な運用体制を整備する必要があります。
共同利用が許されている理由と具体例
個人データの共同利用が容認されている理由は、企業グループ全体での効率的な事業運営とサービス品質の向上にあります。グループ企業間で顧客に関する情報を適切に共有することで、より質の高いサービスを提供し、顧客満足度向上が期待できるからです。
また、グループ内での情報連携は、業務プロセスの簡素化にも寄与します。各社が独自に情報を管理し、都度やり取りをするよりも、一元的な管理のもとで必要な情報を共有する方が効率的です。たとえば、航空会社グループでは、航空会社本体と系列ホテル、観光会社の間で予約情報や顧客データを連携しています。
これにより、航空券とホテル宿泊をセットにした魅力的な旅行プランの提案や、マイレージポイントの相互利用が実現し、顧客の利便性が向上しています。したがって、グループ企業間でのデータ活用は、顧客へのサービス向上と業務の効率化を両立させる重要な取り組みです。ただし、その実施には適切な管理体制の構築と運用ルールの整備が欠かせません。
個人データの「第三者提供」と「共同利用」との違い
個人データの第三者提供と共同利用には、法的な違いがあるのをご存じでしょうか。第三者提供は原則本人の同意が必要ですが、共同利用では事前に利用目的などを公表すれば、原則、本人の同意なしでの情報共有が可能です。上記2つの違いは、情報を受け取る側の立場に基づいています。第三者提供では、情報を受け取る事業者は独立した第三者として扱われます。
一方、共同利用では受け取る側は共同で事業をおこなうパートナーとしての位置づけです。例として、ある百貨店が顧客情報を外部の保険会社に提供する場合は第三者提供に該当し、顧客の同意を得る必要があります。しかし、百貨店グループ内で百貨店とグループ会社が顧客情報を共有する場合は共同利用として扱われるため、適切な事項の公表があれば顧客の同意は不要です。
以上の点から、第三者提供と共同利用は情報共有する相手との関係性、利用範囲によって区別され、それぞれに適した法的手続きが求められます。
個人データの「委託」と「共同利用」との違い
個人データの委託と共同利用は、情報の利用目的と責任の所在に大きな違いがあります。なぜなら、委託では委託元の指示で個人データを取り扱いますが、共同利用では各事業者が対等な立場で個人データを利用するためです。一例として、百貨店が顧客データの入力作業を外部業者に依頼する場合は委託に該当し、外部業者は百貨店の指示に従って作業をおこないます。
これに対し、百貨店グループ内での顧客情報の共有は共同利用であり、各グループ会社が独自のサービスを提供するために情報を活用します。したがって、両者では個人データの取扱いや責任の所在が異なるため、目的に応じて適切な方法を選ぶ必要がある点は理解しておきましょう。
個人データの共同利用を行うための要件


個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人データを共同利用するには、5つの要件を満たす必要があります。要件が設けられる理由は、個人データの取扱いの透明性確保とともに、個人の情報がどのように利用されているかを把握できるようにするためです。そして、個人データを共同利用する際は、次の項目を抑えておく必要があります。
具体的な要件は以下の5項目です。
- ・共同利用をする旨
- ・共同利用して利用される個人データの項目
- ・共同利用する者の範囲
- ・利用する者の利用目的
- ・当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人であっては、その代表者の氏名
上記5つの要件を満たし、本人が容易に知り得る状態にすることで、はじめて適法な共同利用ができます。しかし、要件のひとつでも欠けると共同利用としては認められないため、注意が必要です。
WEBページに掲載する際の注意点
個人データの共同利用をWEBページに掲載する際は、利用者の理解と法令遵守の両面から適切な情報開示が重要です。なぜなら、個人情報保護法では本人が容易に知り得る状態での情報公開が求められているためです。
WEBページへの掲載で具体的に注意する点は以下の5点です。
- ・閲覧者が理解しやすい表現を心がける
専門用語や難しい言葉は避け、具体例を交えながら説明します。例として「個人データの利用目的」という表現よりも「お客様の個人情報を使用する目的」のほうが理解しやすいでしょう。
- ・法令違反に該当する内容がないか確認をおこなう
個人情報保護法や関連法規の要件を満たしているか、法務部門や専門家のチェックも法令違反を未然に防ぐための有効な手段といえるでしょう。
- ・免責事項の掲載もする
情報の正確性や更新頻度、利用に関する制限事項などを明記し、利用者との間で適切な理解を共有します。
- ・著作権や肖像権に関する記載も必須
掲載されている情報の権利関係を明確にし、無断転載や不正利用を防止する必要があります。
- ・SSLセキュリティやCookieの扱いについても明記する
利用者のプライバシーとセキュリティを保護するための技術的対策や、Cookieを通じて収集される情報の範囲と目的を説明します。
以上の要素を組み合わせることで、利用者にわかりやすく、かつ法的要件を満たした情報開示ができますが、定期的な内容の見直しと更新も忘れずにおこないましょう。
共同利用後に本人の同意なく変更はできる?
個人データの共同利用開始後は、原則、本人の同意なく「共同して利用される個人データの項目」及び「共同して利用する者の範囲」について変更はできません。このことは、個人情報保護法で定められた規定であり、個人の権利利益を保護するためのルールだからです。また、共同利用の内容を勝手に変更してしまうと、本人が想定していない形で個人情報が利用される恐れがある点も大きな要因です。
百貨店グループを例にあげると、店舗運営会社間でのみ顧客情報を共同利用していた場合、新たにグループ外の通販会社を共同利用者に追加することは、「共同して利用する者の範囲」の変更に該当します。また、共同利用する個人データの項目を「氏名・住所・電話番号」から「クレジットカード情報」まで拡大することは、「共同して利用される個人データの項目」の変更として扱われます。
ただし、すべての変更に本人の同意が必要なわけではありません。共同利用者の名称が変更になった場合や、住所表記が変わった場合など、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内は、本人の同意なく変更が可能です。重要な点としては、変更が本人の権利利益に実質的な影響を及ぼすかどうかです。
それのため、個人データの共同利用後の変更には慎重な判断が求められます。本人の権利利益を守りながら適切な情報を利用するには、変更の重要性を見極め、必要に応じて本人の同意を得る手続きが大切です。
共同利用者の範囲について
個人データの共同利用者の範囲は、個人情報保護法の要件であり、本人が自分の情報をどの事業者まで将来利用されるのかを正確に把握するため、共同利用者の範囲を定める際は、企業名や事業者の属性の具体的な名称等が求められます。
仮に、金融グループの場合「○○銀行グループ」などの曖昧な表現ではなく「○○銀行、○○証券、○○カード」のように個別の事業者名を列挙します。
したがって、共同利用者の範囲は透明性と具体性を確保しながら、実務上の必要性とのバランスを見て設定した方がよいでしょう。
個人データの共同利用における「管理責任者」とは?
個人データの共同利用における管理責任者は、共同利用する個人データの取扱いに関する包括的な責任を負う者です。管理責任者は、個人情報の安全管理や苦情対応など、共同利用全般の管理・監督を担う重要な役割を果たします。管理責任者を配置する理由は、個人情報保護法で定められた義務を適切に履行し、本人の権利利益を保護するためです。
複数の事業者間で個人データを共有する場合、統一的な管理体制がなければ、情報の取扱いに混乱が生じるかもしれません。それゆえ、管理責任者を定め、責任の所在を明らかにすることで適切な情報管理を可能にしています。
具体例として、大手製造業グループでは、持株会社のコンプライアンス部門長が管理責任者として指名され、グループ全体の個人情報保護体制を統括しています。なお、管理責任者には、個人データの取扱いに関する規程の整備や安全管理措置の策定と実施、本人からの開示請求など、幅広い業務に対応しなければなりません。
そして、共同利用の実施状況を定期的に確認し、必要に応じて改善措置を講じる役割も担います。以上の点から、管理責任者は共同利用における要となる存在であり、その役割を適切に果たすことで、個人情報の保護と円滑な事業運営の両立ができます。
共同利用においてはルールを定めることが一般的
個人データの共同利用を実施する際は、明確なルールの策定が欠かせません。データの取扱い方法や安全管理措置、責任分担などの重要事項を詳細に定める必要があります。これは、共同利用する各事業者で取り扱い方に違いが生じないようにするためでもあります。
そして、事故や紛争が発生した際の対応手順を明確にし、迅速な解決を図ることも重要な目的のひとつです。また、個人情報保護法の要件を満たし、本人の権利利益を保護する観点からもルール化は不可欠といえます。
たとえば、大手物流企業グループでは、配送業務の効率化のため、グループ企業間で顧客の配送先情報や履歴を共同利用しています。この際「個人情報共同利用規程」を定め、データの保管方法や更新手順、アクセス権限の設定などを明文化しています。次に、配送事故発生時の報告体制や緊急対応手順も規定し、グループ全体で統一的な対応を実現しています。
このように、共同利用のルールを明確に定めることで、安全かつ効率的な個人情報の活用が可能です。
取得済みの個人データを共同利用するときの注意点
取得済みの個人データを共同利用する際は、利用目的の範囲内で実施する必要があります。個人データを取得する時点で本人に示した利用目的に沿った取扱いを確保し、本人の予測可能性を担保するためです。ただし、取得時の利用目的と共同利用時の目的説明は、表現を完全に一致させる必要はありません。
たとえば、通信販売会社が会員登録時に「関連会社との共同利用により、関連する商品のサービス提供のため」と説明していた場合、後日グループ会社と共同利用する際は「関連する商品
のアフターサービスに関するお知らせのため」などの表現も許容されます。
そのため、取得済みの個人情報を共同利用する場合は、本人に示した利用目的の本質的な範囲を逸脱しないよう留意しながら、実務に即した柔軟な運用が求められます。
まとめ
今回は個人情報の共同利用について、定義から実務上の注意点まで幅広く解説しました。共同利用制度を適切に活用するには、法令要件の遵守と実務的な配慮のバランスが重要です。明確なルール設定と適切な運用により、個人情報保護と業務効率化の両立を目指しましょう。

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士