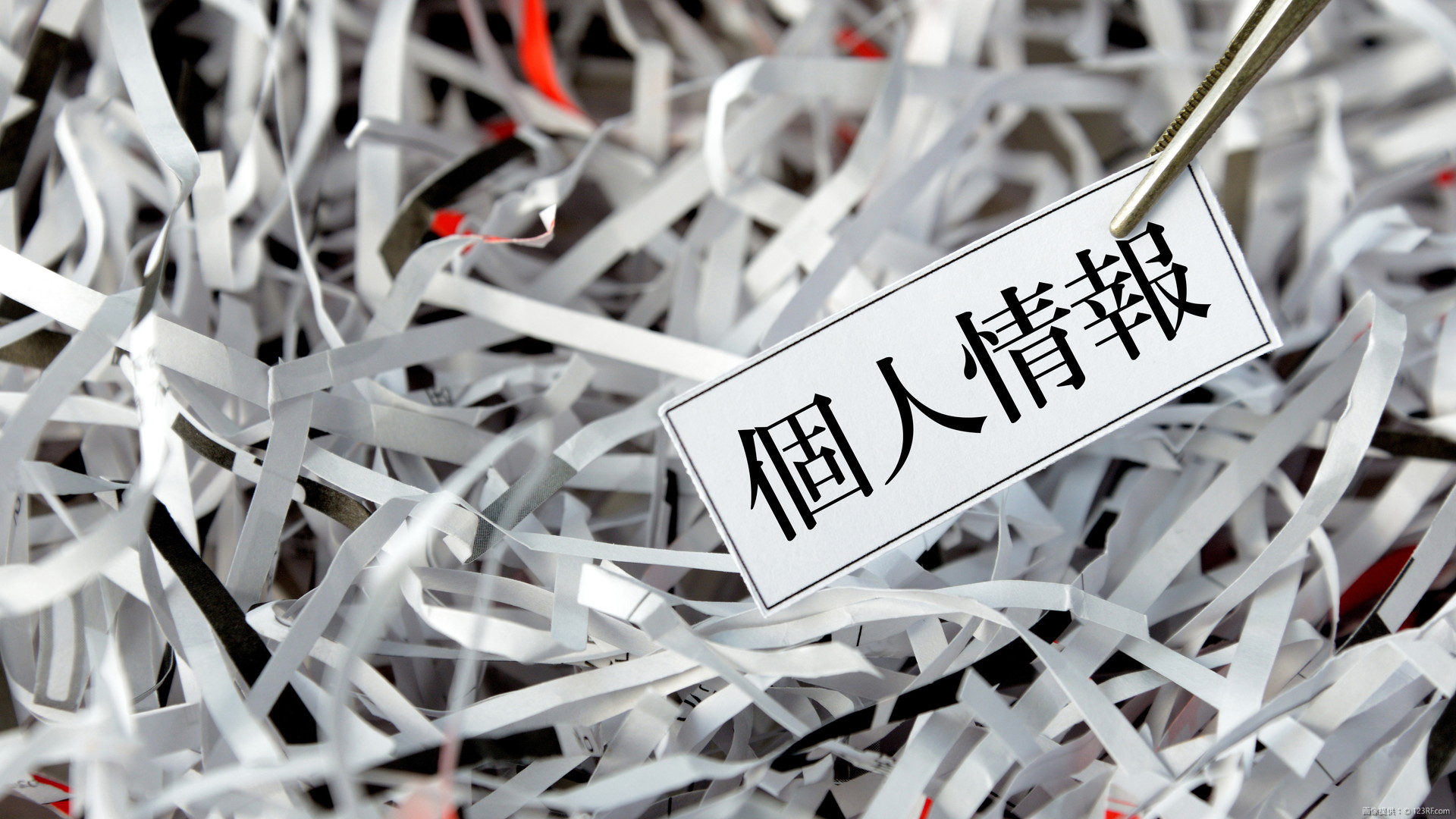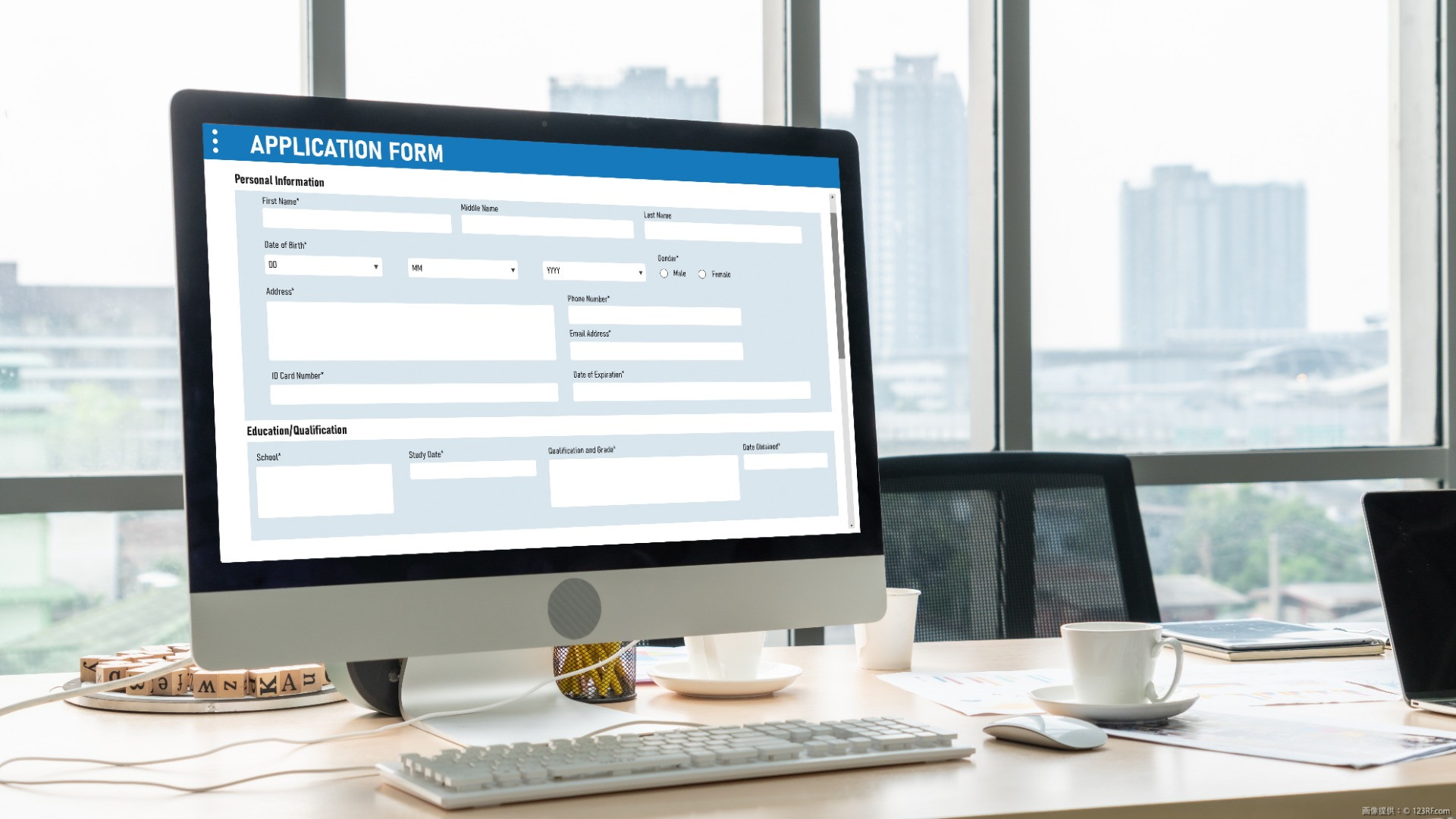個人情報とは?定義や具体例などの基本をわかりやすく解説
2025.1.10

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人情報とは?定義や具体例などの基本をわかりやすく解説
インターネットが発達した現代社会では、スマートフォンは多くの人の必需品です。そして、SNSやネットショッピングを使うとき、さまざまな場面で「個人情報」を晒しているのをご存じでしょうか。しかし、私たちが提供する情報の範囲、また定義を正しく理解している人は少ないかもしれません。そこで、今回は個人情報の定義や具体例などをわかりやすく解説します。

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人情報とは?


個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
日常生活で扱われる「個人情報」は、オンラインショッピングや各種会員登録など、あらゆる場面で利用しています。しかし、情報自体の取り扱いを誤ると、深刻な事態を招くかもしれません。そこで、以下では個人情報の定義や具体例を詳しく紹介します。
個人情報の定義
個人情報保護法では、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」と定めています。本定義は、自分自身が保有する情報を適切に保護し、その利用を適正に管理する基準を示しています。なお、個人情報は名前や住所といった基本的なものから、顔写真、指紋データなどまで幅広い情報が含まれます。
とくに重要なのは、単独では個人を特定できないものでも、ほかとの組み合わせることによって個人情報として扱われる点です。具体的には、社員番号や学籍番号は単体では個人を特定できませんが、所属する組織内では個人を識別するものとして機能します。
また、インターネット上のIPアドレスやクッキー情報なども、状況によっては個人情報に該当する可能性があります。以上の点から、個人情報は私たちの生活に密接に関わる重要な情報であり、正しい理解と適切な取り扱いをしなければなりません。
個人情報に該当する例
個人情報には多様な種類があるのをご存じでしょうか。日常生活で頻繁に使用される基本的な情報から、近年のデジタル化に伴って重要性を増している電子的な個人識別情報まで幅広い情報が含まれます。以下では、代表的な例を詳しく解説します。
氏名
氏名はもっとも身近で基本的な個人情報です。姓名の組み合わせにより、特定の個人を識別する重要な要素です。たとえば、日本の代表的な苗字である「鈴木」や「田中」だけでは、個人と断定できませんが、名前まで加わることで個人として認定できる情報になり得ます。また、ローマ字表記や通称名、旧姓なども個人を特定できる情報として扱われます。
住所・電話番号・生年月日等
住所は個人の居住地を示す重要な個人情報です。電話番号も同様に、固定電話や携帯電話を問わず、個人と直接つながる連絡手段として重要視される情報です。そして、生年月日は年齢確認や本人確認に使用されるオーソドックスな個人情報であり、ほかの情報と組み合わせによって個人の特定につながります。
メールアドレス
メールアドレスは、デジタル社会における重要な個人情報です。とくに、氏名や所属組織が含まれるメールアドレスは、それ自体で個人を特定する情報として認識されます。また、プライベートで使用する個人メールアドレスも、アカウント登録や各種サービスの利用に紐づけられれば、個人を識別する情報といえます。
パスポート番号等
パスポート番号は、国際的な身分証明として使用される重要な個人情報です。そして、パスポート番号以外にも、運転免許証番号やマイナンバー(個人番号)、健康保険証番号なども、公的な個人識別符号として扱われます。これらの番号は、厳重な管理が必要な重要な個人情報といえるでしょう。
顔認証データ等
顔認証データは、生体認証技術の発展により重要性を増している個人情報です。顔写真やその特徴データに加え、指紋データ、虹彩パターン、声紋なども生体認証に使用される個人情報として扱われます。こうした最新技術を用いたデータは、高度なセキュリティシステムで保護される必要がある機密性の高い個人情報です。
個人情報に該当しないもの
日常生活やビジネスで用いる「すべての情報」が個人情報に当てはまるわけではありません。個人と紐づかないもの、または故人は該当しません。個人情報保護法が「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」が保護対象だからです。
なお、該当しない例としては、企業の従業員数や平均年齢、統計情報として集計されたデータは対象外です。また、歴史上の人物や他界している著名人の情報も、現存していないため、個人情報としては扱われません。
ただし、個人情報に該当しなくても、取り扱いには一定の配慮が必要です。単独では個人を認識できなくても、複数の組み合わせで個人を特定できる可能性があるからです。そのため、情報の性質や利用状況に応じて、適切な管理と運用が欠かせません。
個人情報と間違えやすい用語
個人情報に関連する用語には、似て非なるものが数多く存在します。これから紹介する用語は一見似ていますが、法律上の意味や扱いが大きく異なるため注意が必要です。それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
「要配慮個人情報」とは
差別や偏見につながりやすい機微な個人情報を指します。こちらの情報区分は、一般の個人情報以上に厳格な取り扱いが求められます。なぜなら、情報漏洩によって本人の権利や利益が著しく侵害される恐れがあるためです。具体的には、人種や信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪被害の事実などが「要配慮個人情報」に該当する場合があります。
また医療機関が保有する患者の病歴データ、障がい者手帳の情報などは、要配慮個人情報として扱われます。したがって「要配慮個人情報」はプライバシー保護の観点から特別なケアを必要とする重要な情報区分であり、取得や利用には本人の同意が原則必要です。
「個人情報データベース等」とは
個人情報を含む情報の集合物を体系的に整理し、検索可能な状態で管理している情報です。電子データやアナログデータを問わず、特定の規則に従って整理された個人情報の集合体は、すべて個人情報データベース等に該当します。
たとえば、顧客管理システムや従業員名簿、会員情報リスト、診療カルテなどがあげられます。これらは体系的に整理され、必要な情報を容易に検索・抽出できる状態で保管するのが一般的です。そのため、個人情報データベース等は、組織による個人情報の効率的な管理と活用を可能にする一方、適切な安全管理措置が求められる重要な情報資産といえます。
「個人データ」とは
個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことです。企業や組織が事業活動のなかで日常的に利用する個人情報の大部分が、このデータに該当します。個人データは、データベースに収録された時点で、重要度の高い情報として位置づけられます。
企業の顧客データベースに登録された氏名や連絡先、オンラインショップの会員情報、病院の電子カルテシステムに保存された患者情報などが個人データに該当します。個人データを取り扱う事業者は、安全な管理と適切な取り扱いが求められ、情報の漏洩や紛失を防ぐための具体的な措置を講じなければなりません。
「保有個人データ」とは
保有個人データとは、個人情報取扱事業者が開示や内容訂正、追加又は削除、利用停止、消去及び第三者への提供への停止を行うことのできる権限を持つ個人データのことです。個人情報保護法では、本人からの開示請求や訂正要求に応じる義務を事業者に課しているため、この概念が重要な意味を持ちます。実際には、企業の顧客管理システムに保存された会員情報や、医療機関が保有する患者の診療記録などが保有個人データの対象です。
ただし、本人や第三者の権利利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものは、保有個人データから除外されます。保有個人データは、個人の権利保護と事業活動の両立を図るための重要な情報であり、事業者には適切な管理と本人からの各種請求への対応が求められます。
個人情報を取り扱う際の基本的なルール


個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人情報の取り扱いは、企業や組織にとって重要な責務です。不適切な管理や運用は、情報漏洩やプライバシー侵害につながり、深刻な問題に発展するかもしれません。そのため、企業の信頼性を高めるには、個人情報を扱う際のルールの遵守が必要不可欠です。そこで、以下では個人情報の取得から開示までの基本的なルールを解説します。
取得・利用のルール
個人情報の取得と利用には、利用目的の特定と本人への通知又は公表が必要です。これは個人の権利を保護し、情報の適切な管理を確保するための原則です。個人情報を取得する際は、利用目的を具体的に特定し、本人に通知または公表しなければなりません。
また、取得した情報の使用範囲を明確にすることで、不正利用や目的外使用を防ぎ、透明性の高い情報管理を維持するのも大きな要因です。具体例として、WEBサイトでの会員登録時には、氏名や連絡先などの個人情報を取得する目的(商品の発送、サービスの提供、お知らせの送付など)を明示します。
また、アンケート調査を実施する場合は、回答内容の使用目的や保管方法について事前に説明する必要があります。
以上のように、個人情報の取得・利用においては、目的の明確化を徹底することが、適切な情報管理の第一歩です。
保管・管理のルール
個人情報の保管・管理では、適切な安全管理措置を講じ、情報の紛失や漏洩を防止する必要があります。なぜなら、情報漏洩は個人の権利侵害だけでなく、組織の社会的信用の失墜や法的責任につながるからです。管理方法の例として、物理的な対策では、個人情報を含む書類の施錠保管やシュレッダーによる確実な廃棄があげられます。
技術的な対策としては、パスワード設定やアクセス権限の制限、データの暗号化などの実施です。そして、人的な対策としては、定期的に従業員に対して「個人データの取扱いに関する留意事項」などの研修を開催し、知識やリスクへの理解を促しています。また、
組織体制の整備も重要な取り組みのひとつです。
なお、現場の実例として、医療機関では患者の診療記録を厳重に管理し、アクセス権限を持つ職員を制限しています。続いて、教育機関においては学生の成績データや個人記録を専用のデータベースで管理し、アクセスログの記録や定期的なバックアップを取るのが基本です。
このように、個人情報の保管・管理には、安全管理措置と継続的な改善が必要不可欠です。
第三者へ提供する際のルール
個人情報をほかの方へ提供するとき、本人の同意は欠かせません。個人の権利やプライバシーを保護し、情報の適切な管理を確保するための基本的な要件です。提供した内容は、使用方法や管理体制によって、予期せぬリスクや被害が生じる可能性があるため、慎重に扱わなければなりません。
したがって、グループ会社間での情報共有やマーケティング目的での情報提供においても、利用目的や提供される情報の範囲を明確にし、本人の承諾を得なければなりません。
ただし、法令に基づく場合や人の生命・身体・財産の保護に必要な場合など、一定の例外事由に該当する際は、本人の同意なしでも認められます。このように、第三者提供のルールは、個人情報の適切な流通と保護のバランスを取るために設けられています。
保有個人データの開示を求められたときのルール
個人情報を取り扱う事業者は「保有個人データ」の開示請求を受けたとき、基本的に開示しなければなりません。対象者の権利とプライバシーを尊重するためあり、自分の情報を確認し、必要に応じて訂正や利用停止を求める機会の保障は、個人情報保護の基本的な考え方に基づいています。
ただし、開示により他人の利益を害する恐れがある場合や、当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を与える可能性があるときは、開示拒否できる例外規定も設けられています。
実例としては、医療機関が患者から診療記録の開示を求められたケースや企業が顧客から会員情報の開示を請求された場合があります。
以上の点からもわかるとおり、保有個人データの開示請求への対応は、個人の権利保護と事業活動の両立を図るための重要な取り組みです。
事業者は開示請求に関する手続きを明確化し、迅速かつ適切な対応ができる体制づくりが必要不可欠です。
個人情報保護法違反をした場合の責任
個人情報保護法に違反すると、刑事、民事、また社会的な責任が発生します。私たちの情報が現代社会において重要な価値を持ち「情報を守ること」が、社会全体の信頼関係を支える基盤だからです。法人に対する罰金刑や対象者への懲役刑といった刑事罰が科されるほか、損害賠償請求などの民事責任も生じます。
実例として、大阪高裁の判例では、システム開発の委託業務に従事していたアルバイト従業員が住民基本台帳データを不正にコピーし、名簿販売業者へ販売した事件がありました。本事案では21万人分もの個人情報が流出し、関係者は厳しい処分を受けただけでなく、組織の信用も大きく失墜しました。
このように個人情報保護法違反は、組織と個人の双方に重大な影響を及ぼすため、適切な管理体制の構築と継続的な教育が不可欠です。
まとめ
今回は個人情報の定義から具体例、取り扱いルール、法令違反時の責任まで幅広く解説しました。個人情報は日常生活に深く関わる重要な要素であり、適切な保護と管理は、私たち一人ひとりの権利を守るために不可欠です。今回の記事を参考に、個人情報に対して正しい知識を持ち、慎重に取り扱うように心がけましょう。

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士