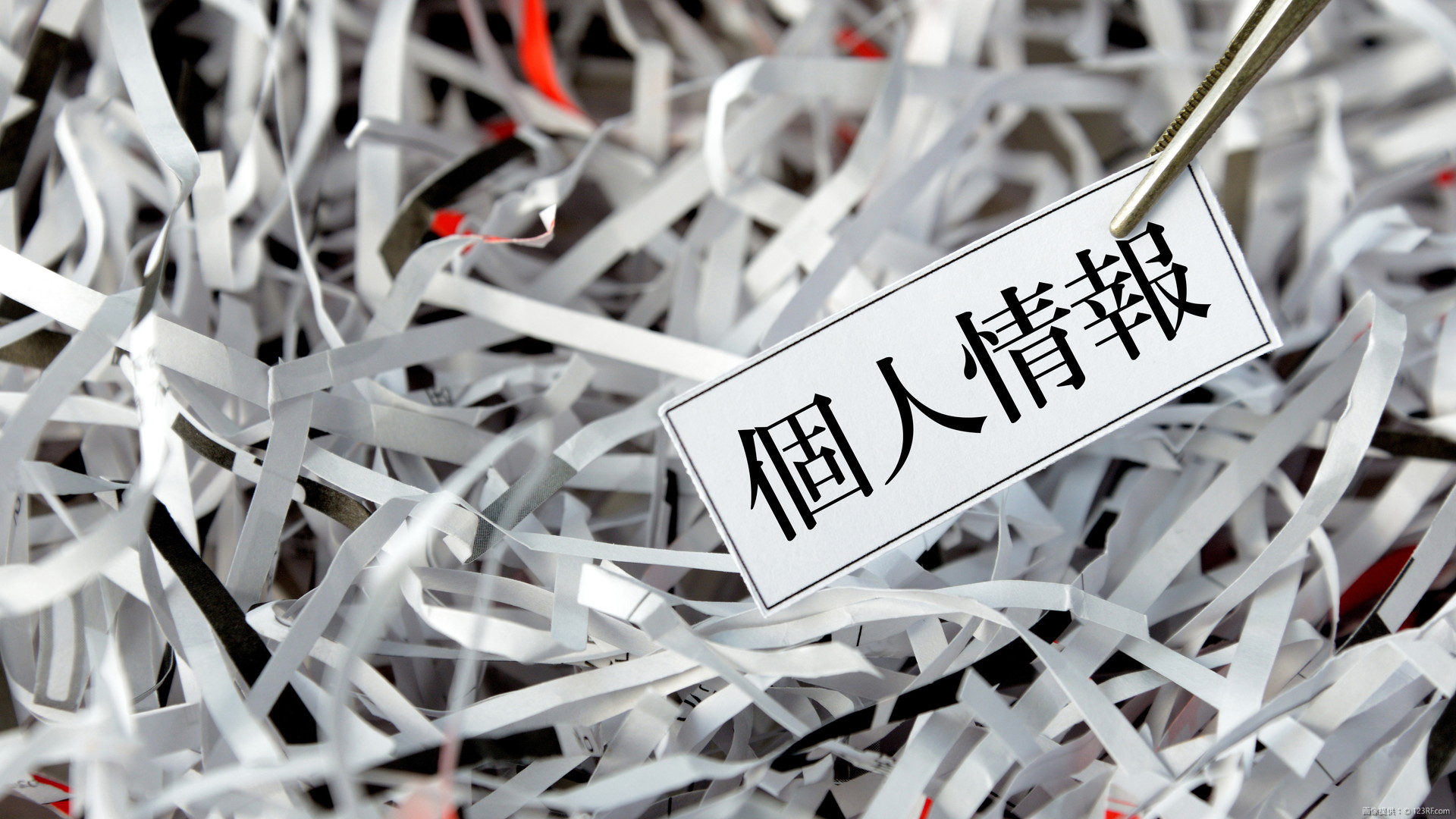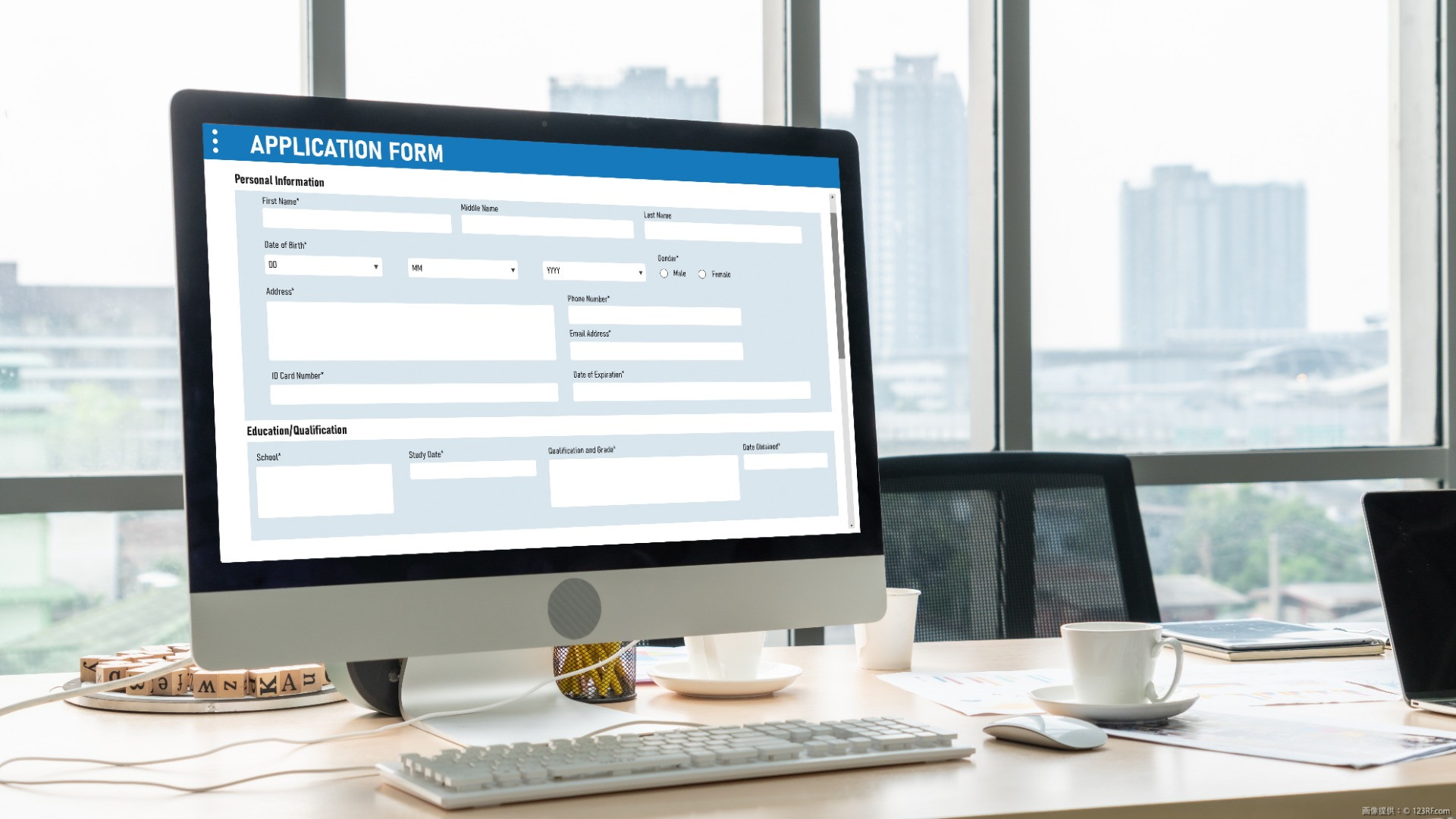
個人データの第三者提供とは?定義・ルールを解説
2025.1.10

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人データの第三者提供とは?定義・ルールを解説
デジタル社会の進展により、企業間でのデータ共有が日常的におこなわれています。しかし、顧客の大切な情報を他社と共有する際のルールを理解していないと、思わぬトラブルを引き起こすかもしれません。そこで今回は、個人データ管理の基本から実務での注意点まで、企業が知っておくべき重要な知識をわかりやすく解説します。

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人データの「第三者提供」とは?


個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
事業者が保有する顧客情報を、別の企業や組織に渡す行為は厳格な規制の対象です。プライバシーの保護や情報セキュリティの観点から、データの取り扱いには細心の注意が求められるためです。企業間での情報の受け渡しは、サービスの向上やビジネスの発展に不可欠な要素です。たとえば、通信販売会社が保有する購入履歴を関連会社と共有すれば、顧客に合わせた商品提案が可能になるでしょう。一方で、本人の意図しない目的でデータが利用されるリスクも存在するため、適切な個人データ管理体制の構築が重要です。
なお、個人データを引き渡す際は、原則本人からの同意を得る必要があります。ただし、警察からの要請や業務委託先への提供など、同意が不要なケースも定められています。企業は法律に基づく手続きを踏んで情報提供し、個人の権利を守りながらビジネス展開しなければなりません。
デジタル社会の発展に伴い、企業間でのデータのやり取りは増加の一途をたどっています。そのため、個人データの適切な管理と保護は、企業の重要な責務といえます。
第三者提供は、原則本人の同意取得が必要
個人データを外部に渡す際は、事前に本人から同意を得る必要があります。プライバシーの保護と個人データの適切な管理を徹底し、本人の権利を守るためです。企業は、顧客から取得した個人情報の利用目的や提供先を明確に説明し、同意を得なければなりません。
例えば、グループ企業間でのデータの受け渡しも、本人の同意なしには実施できません。
企業は、顧客から同意を得る際に、分かりやすい説明と透明性の高い手続きを心がける必要があります。同意取得は、顧客との信頼関係を築き、円滑なビジネス運営を実現するための重要な要素です。
第三者提供で本人の同意が不要なケース


個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人情報保護法では、一定の条件下であれば、本人の同意を得ずに第三者提供が認められる例外規定が設けられています。ここでは、例外規定が認められる3つのケースを紹介します。
法令に基づく場合
警察や裁判所からの要請があった場合、個人データを提供する企業は本人に同意を得る必要はありません。法令に基づく正当な理由があり、社会秩序の維持や犯罪捜査に必要不可欠だからです。たとえば、詐欺事件の捜査で被害者への送金記録の提出を求められた金融機関は、本人の同意を得ることなく個人データを警察に提供します。
また、裁判所から文書提出命令を受けた企業は、顧客との契約内容や取引履歴を開示する義務を負います。ただし、法令に基づく要請であっても、必要以上の情報を開示すれば、顧客との信頼関係を損なう恐れがあるため、企業は法務部門と連携し、適切な判断のもとで個人データを提供する体制を整える必要があります。
人の生命・身体・財産の保護に必要な場合で、本人の同意を得ることが困難なとき
人命救助や重大な財産被害の防止が必要な場合で、本人の同意を得ることが困難なときは、本人の同意がなくても個人データの第三者提供が認められます。緊急性が高く、本人から同意を得る時間的余裕がない状況において、より大きな利益を守るために設けられた例外規定です。たとえば、持病を持つ従業員が職場で突然倒れた場合、救急隊員へ既往歴や服用中の薬の情報を提供するケースが該当します。
また、銀行が不正取引を検知し、被害を防ぐため、ほかの金融機関と顧客データを共有する場合も例外規定の対象です。したがって、人の生命・身体・財産の保護を目的とし、本人の同意を得ることが困難な場合における個人データの第三者提供は、提供する情報の範囲を必要最小限に留め、緊急性や提供の必要性を慎重に判断しなければなりません。企業は、この例外規定の趣旨を正しく理解し、適切な運用を心がける必要があります。
公衆衛生の向上・児童の健全育成に必要な場合で、本人の同意を得ることが困難なとき
公衆衛生の向上や児童の健全育成に必要な場合で、本人の同意を得ることが困難なときも、本人の同意なく個人データを第三者に提供できます。感染症予防や児童虐待の防止など、社会全体の利益に関わる重要な課題に対応するために設けられた例外規定です。
一例として、保健所が感染症対策のために医療機関から患者の行動履歴を入手する場合や、児童相談所が虐待の疑いがある児童の情報を学校から収集するケースなどです。しかし、提供する個人データは目的達成に必要な範囲内に限定し、関係機関との連携を図りながら適切に管理する必要があります。
企業や組織は、公衆衛生の向上や児童の健全育成という社会的責任を果たしつつ、個人データの適正な取り扱いに努めなければなりません。
第三者提供の取り扱いルール
個人データを第三者に提供するときは、提供側と受け取る側の双方に、それぞれ異なる義務と責任が課されます。ここでは、第三者に個人データを提供する際に理解すべき「ルール」を紹介します。
個人データを提供する側
顧客の個人データを他社に提供する企業には、厳格な管理体制と透明性の高い手続きが求められます。個人データを扱う企業は、顧客の権利を守り、信頼関係を維持するために、適切な個人データ管理を実践する責任があるためです。仮に、通信会社が新サービスの案内のために顧客リストを活用する場合、利用目的の明示や提供停止の機会確保など、細かな配慮が必要です。
提供する企業は、個人データの利用目的や提供先を明確に説明し、顧客が自身の個人情報をコントロールできる環境を整えます。顧客への通知方法は、メールやWEBサイト、書面など、確実に情報が伝わる手段を選択しなければなりません。また、提供を望まない顧客への対応手順も整備し、迅速な停止措置を講じられる体制を構築します。
とくに近年は、データ提供に関するオプトアウト(事前通知制度)の重要性が高まっているのをご存じでしょうか。本制度は、顧客に事後の拒否機会を設け、異議がない場合にのみ個人データの提供をおこなうものです。ただし、病歴や信条といった優先的配慮が必要な情報(要配慮個人情報)は、対象外とされ、オプトアウトにより第三者へ提供することはできません。企業は、こうした規定を順守しながら、顧客の期待に応える情報活用を進めます。
個人データを受け取る側
個人データを受け取る事業者には、取得時に定めた利用目的の範囲内で活用する義務があります。受け取った個人データの不適切な利用を防ぎ、本人のプライバシーを守るために必要不可欠な要件です。例として、顧客満足度調査のために譲り受けた個人データを営業活動に流用すると、法令違反に該当します。
また、アンケート回答者の属性分析を目的として受け取った個人データを、新規サービス開発に活用するのも不適切な利用に当たるので注意が必要です。受け取り側の企業は、個人データの取得経緯を確認し、適切な管理体制を整備する責任も負います。
万が一、個人データの漏洩や不正利用が発生した場合は、適切な対応策を講じなければなりません。問題発生時の対応手順を事前に定めておくことで、リスクを最小限に抑えられます。
外国にある第三者への提供の取り扱いルール
グローバル化が進む現代のビジネスでは、海外企業とのデータ共有が不可欠です。しかし、国境を越えたデータの移転には特別な規制があり、企業は慎重な対応を求められます。ここでは、外国との情報共有についての「ルール」を紹介します。
本人の同意が不要なケース
外国にある第三者への個人データの提供は、日本と同水準にあると認められる個人情報保護制度を有している国や地域であれば、原則本人の同意なく実施できます。
第三者提供に関する注意点
個人情報を第三者に引き渡すときは、さまざまな点に注意が必要です。以下で説明する3つの注意点を理解していないと、企業にとって大きなトラブルに発展するかもしれません。それでは、3つの注意点を見てみましょう。
原則3年間の保存義務がある
企業が保有する個人データの提供記録は、原則3年間の保管が法律で義務づけられています。個人データの管理責任を明確にし、提供先や提供時期の追跡を可能にするためです。具体的には、顧客リストを取引先に渡した際には、提供日時、提供先の企業名、対象となったデータの項目などを記録し、保管します。
なお、記録の保管方法は電子データや書面など、各企業の実情に合わせた形式を選択できますが、必要に応じて速やかに確認できる状態にしなければなりません。そして、保管期間を経過した個人データは、適切な方法で破棄や消去しますが、それまでの間は改ざんや紛失を防ぐ厳格な管理体制が不可欠です。記録の保管は、企業のコンプライアンス体制を示す重要な要素であり、個人情報保護委員会などの監督機関による立入検査の際にも確認対象となる重要事項です。
本人の申し出による停止義務がある
顧客から個人データ共有の停止要請があった場合、企業は速やかに個人データの提供を中止する義務を負います。これは、自身の個人情報をコントロールする権利を保護し、プライバシーを守るための重要な規定です。たとえば、ポイントカード会員の購買履歴を関連企業と共有している場合、会員から停止の申し出があれば、その時点で個人データの共有を中断しなければなりません。
企業は停止要請に備え、受付窓口の設置や手続きの明確化など、迅速な対応体制を整備する必要があります。顧客の意思を尊重し、要請から実際の停止までの時間を最小限に抑えることで、信頼関係の維持にもつながります。また、停止要請を受けた履歴も適切に記録し、誤って個人データの提供を再開することがないよう、防止策も考えなければなりません。
オプトアウトで提供できない個人データがある
要配慮個人情報や信用情報など、慎重な取り扱いが必要な個人データは、オプトアウト方式による第三者提供が認められません。これらの情報は、個人の権利利益に重大な影響を与える可能性が高いため、法律で厳格な保護が定められています。
例として、病歴や障害の有無などの医療関連情報、犯罪歴に関する情報、与信判断に用いられる金銭的な信用情報は、第三者への提供が禁止されています。また、個人データを不正取得した場合や、オプトアウトにより提供を受けた個人データも、オプトアウト方式による第三者への提供は認められません。
まとめ
本記事では、個人データの第三者提供について、定義から具体的なルール、注意点まで解説しました。第三者提供には、原則、本人の同意が必須であり、外国へや要配慮個人情報の第三者への提供には特別な規制が設けられています。企業は記録管理や保存期間の遵守、本人からの停止請求への対応など、適切な管理体制の整備が重要視されています。

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士