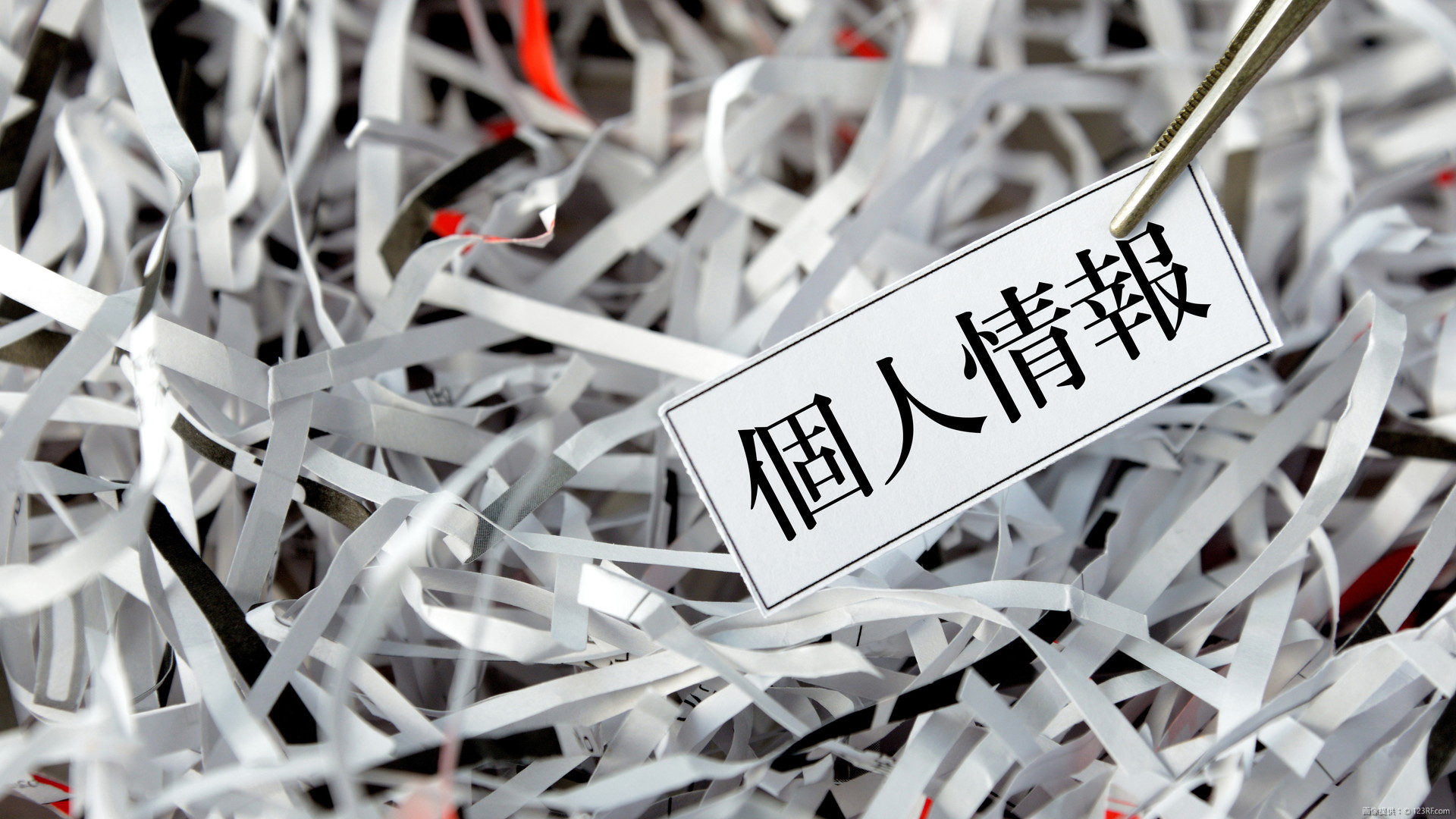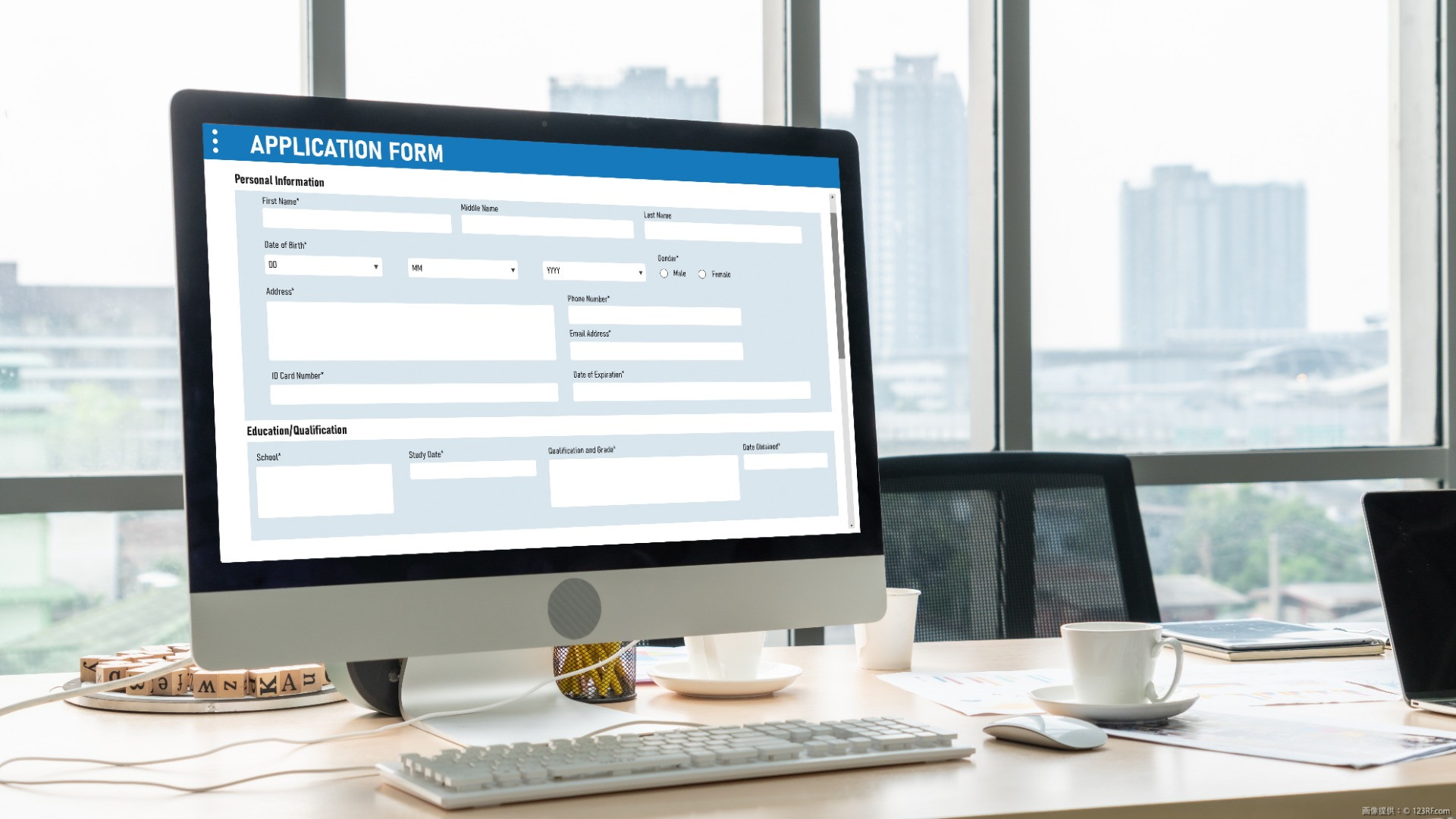【個人情報の漏洩】個人情報保護法に違反した場合の罰則を解説
2025.1.10

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
【個人情報の漏洩】個人情報保護法に違反した場合の罰則を解説
インターネットが進化した現代社会において、個人情報の漏洩は大きな問題です。プライベートな内容から企業の機密情報まで、外部に漏れてはならない情報は多岐にわたります。それでは、具体的にどのようなものが個人情報の漏洩になるのでしょうか。今回は個人情報漏洩の原因から、具体的な罰則について説明します。

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人情報が漏洩する原因


個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人情報の漏洩は、主に5つの要因によって引き起こされます。以下で紹介するケースは、企業の信頼性を大きく損なう可能性があり、適切な予防措置と従業員教育が不可欠です。
- ・ウイルス感染および不正アクセスによる漏洩
システムのセキュリティ対策や運用ルールの徹底が不十分な場合に発生します。マルウェアに感染したメールの開封やフィッシング詐欺による個人情報の窃取が代表的な例です。主なシーンとしては、従業員が不審なメールの添付ファイルを開いてしまい、会社のデータベースに保存された顧客情報が外部に流出するケースがあげられます。
- ・システム障害や不具合による漏洩
サーバーダウンやプログラムのバグにより、個人情報が意図せず外部に公開されてしまう事態が起きています。具体的には、ECサイトのシステム不具合により、ほかのユーザーの注文履歴や配送先住所が表示されてしまうといった事例があります。
- ・セキュリティ対策の不備による漏洩
パスワードの設定が簡単すぎたり、定期的な更新を怠ったりすることで、外部からの侵入を許してしまうケースです。代表例として、退職した元従業員が顧客データにアクセスし、競合他社に持ち出すといった事件が発生しています。
- ・誤表示・誤送信による漏洩
業務上の単純なミスにより、本来知られてはいけない情報が第三者に伝わってしまうケースです。とくに、メールの宛先間違えやCCとBCCの取り違えなどにより、全受信者のメールアドレスが露出してしまうミスが多く発生しています。
- ・紛失や誤廃棄による漏洩
個人情報を含む書類やUSBメモリの取り扱いが不適切な場合、重要な情報が外部に流出する危険性が高まります。たとえば、顧客の個人情報が記載された書類を通常のゴミとして廃棄してしまい、第三者の手に渡ってしまう事例が報告されています。
これらの漏洩要因に対しては、技術的対策と人的対策の両面からアプローチしなければなりません。従業員への定期的な教育研修の実施や情報セキュリティポリシーの見直しにより、個人情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。
個人情報保護法で規定されている定義・義務


個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人情報保護法は、現代社会における個人の権利を守るための重要な法律です。本法律では、個人情報の定義から事業者の義務まで詳細に規定しています。個人情報の適切な運用は、企業の信頼性を左右する重要な要素であり、法令順守は企業の最優先事項といえます。
そもそも個人情報とは
生存する個人を特定できるすべての情報を指します。近年のデジタル技術の発展により、個人情報の範囲は従来よりも広がっています。たとえば、氏名や生年月日などの基本情報だけでなく、顔写真やSNSアカウント、位置情報なども個人情報の対象です。
また、会員カードの購買履歴やスマートフォンの行動履歴なども、他情報との組み合わせによって個人を特定できる場合は個人情報として扱われます。個人情報は私たちの生活のあらゆる場面に存在し、その保護の重要性は年々高まっています。
個人情報の責任を求められる「個人情報取扱事業者」とは
個人情報のデータベース等を事業活動に利用する事業者を指します。この定義は、デジタル化が進む現代社会において、多くの企業や組織に該当します。事業者の規模や業種に関係なく、個人情報を取り扱う以上、法律で定められた責任と義務を負わなければなりません。
個人情報取扱事業者の責務
個人情報取扱事業者には、個人情報の適切な取り扱いと保護に関する厳格な責務が課せられます。なぜなら、個人の権利やプライバシーを守るために不可欠な要件だからです。例をあげると、小売店がポイントカードシステムを運用する場合、顧客の氏名や購買履歴などの個人情報を適切に管理し、目的外利用を防ぐ必要があります。
また、医療機関では患者の診療記録を厳重に管理し、第三者への漏洩を防止する体制を整えなければなりません。それのため、個人情報取扱事業者には、情報の収集から廃棄まで一貫した管理体制の構築が求められます。
個人情報保護法に違反した場合の罰則
個人情報保護法違反は、企業に深刻な影響をおよぼす法的責任を伴います。違反の内容に応じて、企業には厳しい罰則が科され、最悪の場合、経営者や従業員が刑事罰の対象にもなり得ます。個人情報の適切な管理は、現代のビジネスにおいて最も重要な責務の一つであり、その違反は企業の存続すら脅かす重大な問題です。
ここでは、個人情報保護法に違反した場合の罰則を解説します。
個人情報保護委員会からの命令等への違反に対する罰則
個人情報保護委員会からの命令に違反した場合、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。もしも、命令に背いた場合、企業の信頼性を大きく損なうだけでなく、経営者個人の刑事責任も問われる深刻な事態を引き起こすかもしれません。
具体的には、顧客データの安全管理に関する是正命令を無視し続けた企業が、実際に刑事告発された事例もあります。以上の点から、個人情報保護委員会からの命令の軽視は、企業経営において決して許されない重大な違反行為といえるのです。
立入検査に応じなかった場合の罰則
個人情報保護委員会による立入検査を拒否・妨害・忌避した場合、50万円以下の罰金が科されます。この罰則は、個人情報保護法の実効性を確保する重要な規定で、立入検査は個人情報の適切な取り扱いを確認し、法令違反を未然に防ぐ必要不可欠な手段です。
一例として、ある企業が顧客情報の漏洩疑惑を受けて立入検査の通知を受けたにもかかわらず、担当者が検査官の入室を拒否したり、必要な資料の提出を渋ったりした場合が該当します。こうした行為は、個人情報の取り扱いを確認する機会を妨げるものとして、厳しく罰せられます。
立入検査への協力は企業の透明性と信頼性を示す機会であり、企業側が拒否すれば法的制裁だけでなく、社会的信用も大きく損なうため注意が必要です。
個人情報データベース等の不正利用のために盗用した場合の罰則
個人情報データベースなどを不正に利用する目的で盗用した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金でしたが、法改正後は厳罰化され、法人の場合、最高1億円の罰金が科せられる可能性もあります。この厳しい罰則は、個人情報の重要性と不正利用が社会に与える深刻な影響を考慮して定められました。
具体例として、物流業A社に属する従業員が退職時に顧客データベースを持ち出し、競合他社での営業活動に利用しようとした場合などがあげられます。このような行為は、個人のプライバシーを侵害するだけでなく、企業の信頼性も著しく損なう重大な犯罪です。個人情報の不正利用は、デジタル社会における重大な脅威として、厳格な処罰の対象です。
個人情報保護委員会への虚偽報告等に対する罰則
個人情報保護委員会への虚偽の報告若しくは虚偽の資料提出は、50万円以下の罰金という厳しい処罰を受けます。主な理由としては、正確な報告は個人情報保護の基盤を支える重要な義務だからです。また、こちらの罰則は、委員会による監督機能の実用性を確保し、個人情報の適切な管理体制を維持するために不可欠な制度的保障として機能します。
たとえば、情報漏洩事故が発生した際、事故の規模や影響を過小報告する、または対策状況について虚偽の内容を報告するケースなどです。こうした不誠実な対応は、個人情報を保護するうえで重大な違反行為として扱われ、企業の信頼性に致命的な打撃を与える結果を招きます。
個人情報が漏洩した場合の企業のリスク
個人情報の漏洩は、企業に深刻な影響を与える重大な問題です。法的な制裁から経済的損失まで影響の範囲は多岐にわたり、場合によっては企業の存続すら危うくなるかもしれません。ここでは、個人情報漏洩で企業が直面するリスクを詳しく解説します。
違反事実の公表
個人情報漏洩が発生すると、漏洩した事実は個人情報保護委員会のWEBサイトで公表されます。公表される理由としては、個人情報保護法が持つ重要な制裁措置として機能するためです。なお、個人情報漏洩の公表は企業の評判に重大な打撃を与え、ビジネスチャンスの喪失にもつながります。
たとえば、大手通信会社Aの顧客情報漏洩事案では、委員会のWEBサイトで詳細な経緯や原因が公開され、メディアでも大きく報道されました。結果的に新規契約数が大幅に減少し、既存顧客の解約も相次ぎました。このように、違反事実の公表は企業の将来に深刻な影響を及ぼす重大なリスクといえます。
企業の社会的信用低下
個人情報漏洩は企業の社会的信用を著しく低下させる深刻な問題です。情報管理の不備は、顧客や取引先からの信頼を一瞬にして失墜させ、長年かけて築き上げたブランド価値を大きく毀損します。具体例として、大手小売チェーン店では会員カード情報の流出事故後、店舗の来客数が前年比30%も減少し、オンラインショップの売上も激減しました。
さらに、取引先との新規契約が見送られ、既存の取引関係も見直しを迫られるなど、事業活動全体に深刻な影響を与えました。以上を踏まえ、社会的信用の低下は企業の存続自体を脅かす重大なリスク要因といえるでしょう。
改善コストの発生
個人情報漏洩への対応には、多額の改善コストが欠かせません。なぜならば、セキュリティシステムの強化や従業員教育の実施、外部専門家への相談など、さまざまな対策に莫大な費用が発生するからです。
実例として、ある製造業の会社では取引先の情報漏洩後、システム全体の見直しに数千万円以上を投じ、全従業員向けの研修プログラムの実施、セキュリティ専門家の常駐配置など、追加的な安全対策に多額の予算を割く必要がありました。このように、企業が保有する情報が漏洩した際の対応は、企業側に重い財政負担を強いることになるのです。
民事上の損害賠償請求
個人情報の漏洩は、被害者から高額な損害賠償を請求される恐れがあります。漏洩した情報の性質や規模によって、企業は多額の賠償金支払いを余儀なくされ、経営を圧迫する深刻な事態に発展するかもしれません。また、個人のプライバシー侵害は、精神的苦痛に対する慰謝料請求の根拠にもなり、被害者が複数に増える場合は集団訴訟に発展する可能性も高まるでしょう。
金融機関を例にあげると、顧客の口座情報が流出した事案で、数百人規模の被害者から総額で何百万円といった損害賠償を請求されたケースもあります。そのため、個人情報漏洩による損害賠償は、企業の財務基盤を根底から揺るがす重大なリスクといえます。
社内業務の負担が増加
個人情報漏洩への対応は、企業の通常業務に大きな支障をきたします。事実関係の調査や被害者への連絡など、緊急性の高い業務が発生することで社員の負担が急激に増加するためです。さらに、再発防止策の検討にも時間と労力を要し、本来の業務に支障が生じる事態を招きます。
小売業を営む会社の事例では、会員情報の流出後、専任チームを編成して対応にあたりましたが、顧客からの問い合わせだけで、月間100時間以上の追加業務が発生しました。また、通常業務の遅延や従業員の過重労働など、組織全体の生産性が著しく低下する事態に陥りました。このように、企業における個人情報の漏洩は、企業の業務効率を大きく損なう要因となり得ます。
個人情報の漏洩対策はどうする?
個人情報の漏洩を防ぐには、組織全体での包括的な対策が不可欠です。技術的な対策だけでなく、人的な対策も含めた総合的なアプローチが求められます。ここでは、効果的な漏洩対策を3つ紹介します。
- ・従業員への周知・教育を行う
個人情報保護の重要性を理解し、適切な取り扱いができる人材の育成が大切です。定期的な研修やeラーニングをとおして、従業員のセキュリティ意識を高め、情報漏洩のリスクを最小限に抑えます。具体的には、月1回のセキュリティ研修や実例を用いたケーススタディを実施することで、より実践的な知識が身につけられます。
- ・個人情報に関するルールを設定する
明確な管理基準とガイドラインを策定し、組織全体で統一した対応を実現します。個人情報の取得から廃棄までの各段階における具体的な手順を定め、すべての従業員が同じ基準で業務を遂行できる環境を整備します。とくに、個人情報の持ち出し制限やアクセス権限の設定といった運用ルールの明確化が重要です。
- ・セキュリティ体制の構築をする
最新のセキュリティ技術を導入し、システム面での防御を強化します。ファイアウォールの設置やウイルス対策ソフトの導入はもちろん、定期的なセキュリティ監査や脆弱性診断の実施により、システムの安全性を継続的に確保します。また、アクセスログの監視や暗号化技術の活用など、多層的な防御策を講じることで、より強固なセキュリティ体制が実現可能です。
まとめ
今回は個人情報保護法に違反した場合の罰則と漏洩対策について解説しました。個人情報の漏洩は、企業に刑事罰や行政処分、多額の損害賠償、社会的信用の失墜といった深刻な影響をもたらします。そのため、従業員の教育やセキュリティ体制の構築、明確なルール設定など、組織全体での包括的な対策が不可欠です。
個人情報保護は企業の重要な責務であり、継続的な取り組みと改善によって、安全な情報管理体制の確立が求められています。

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士