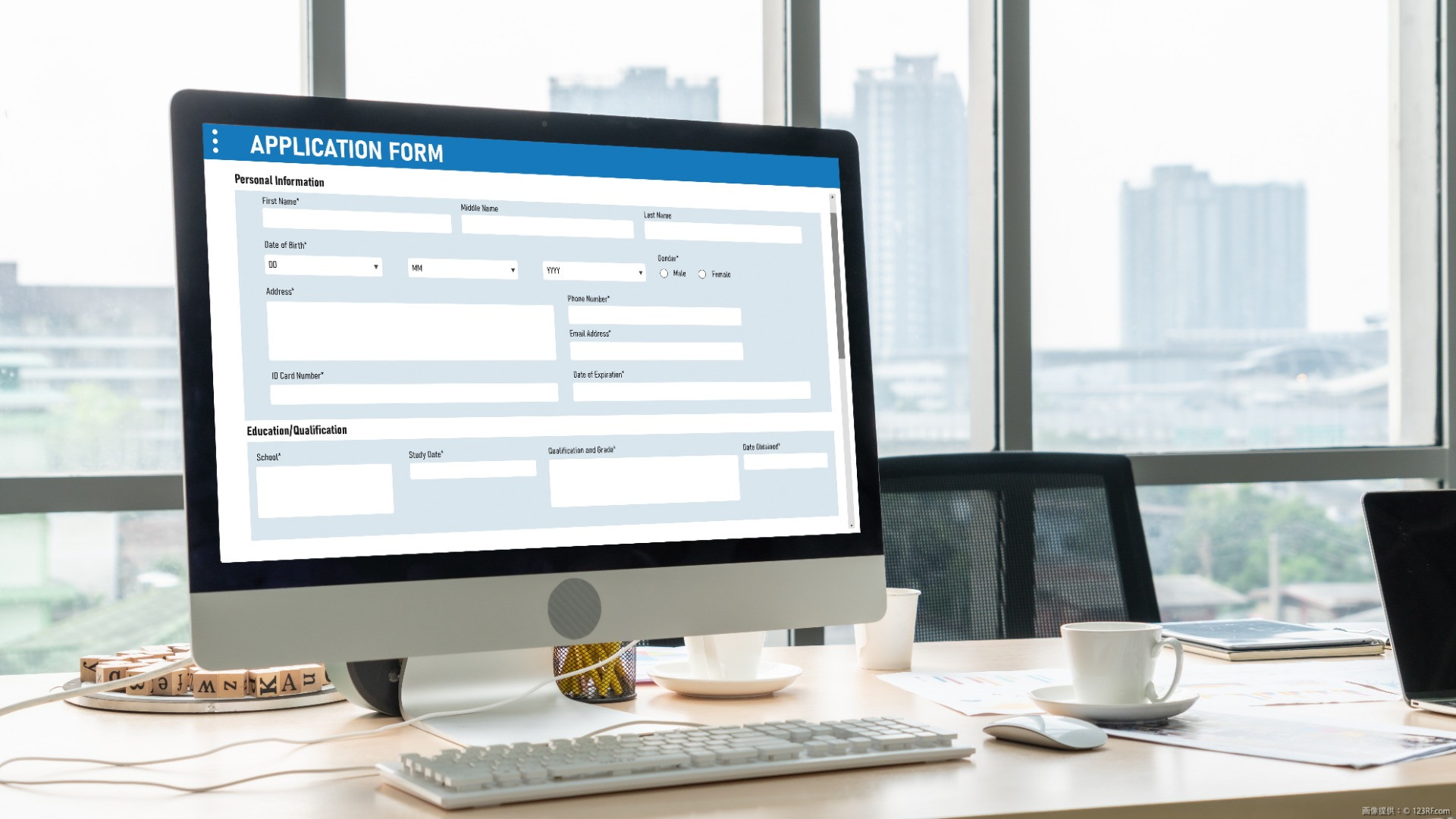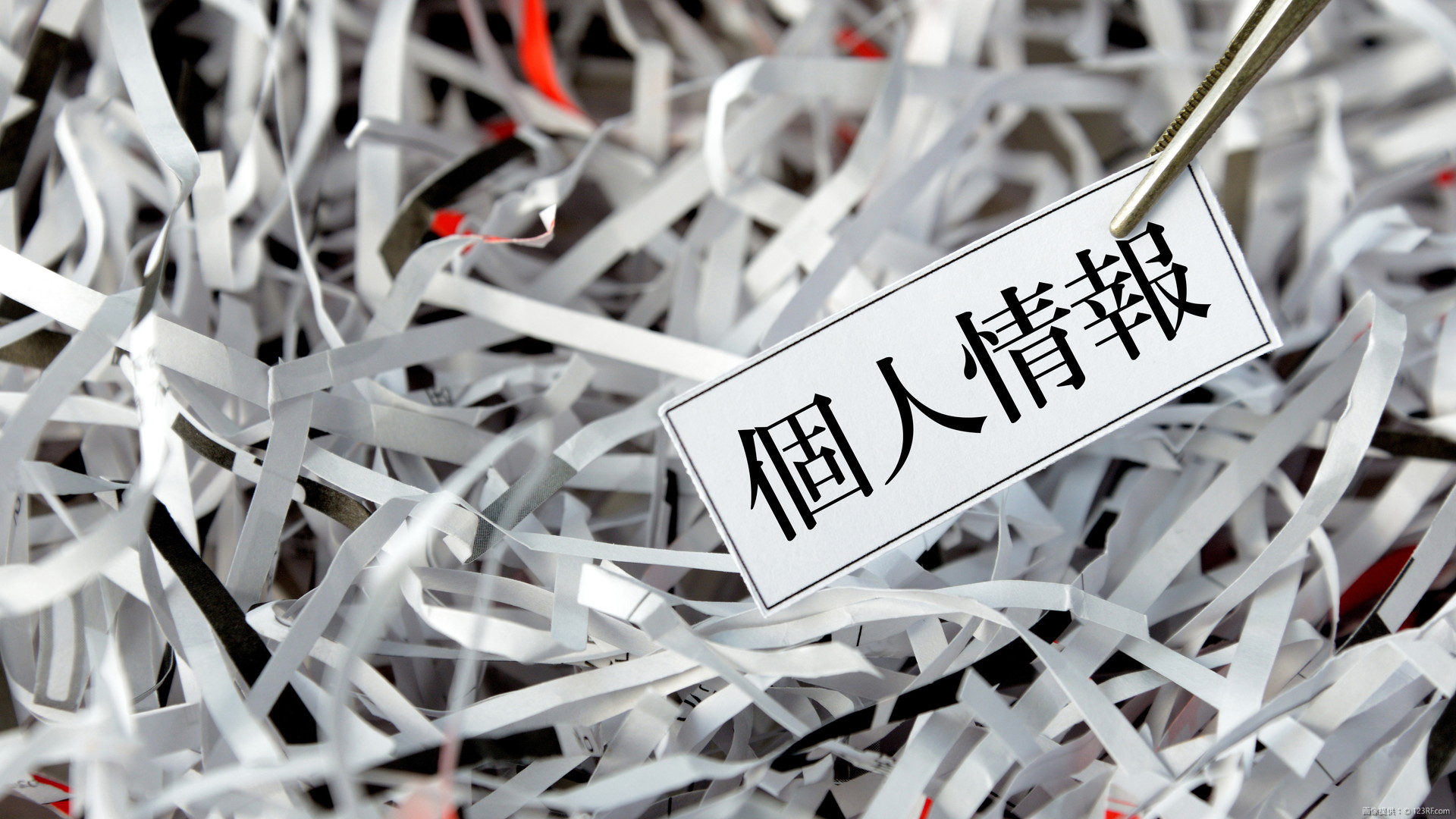
個人情報漏洩対策8つを紹介!個人情報の漏洩やサイバー攻撃から会社を守るには
2025.1.10

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
個人情報漏洩対策8つを紹介!個人情報の漏洩やサイバー攻撃から会社を守るには
昨今、企業における個人情報漏洩事件があとを絶ちません。一度情報が流出すると、企業の信用は大きく損なわれ、多額の損害賠償や業績悪化につながる可能性があります。そこで今回は、企業が実践すべき個人情報漏洩対策について、8つのポイントで解説します。
▶まとめ

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
企業における個人情報漏洩対策が必要な理由


個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
企業の事業継続には、個人情報漏洩対策が不可欠です。現代のビジネスにおいて、インターネットと情報システムは業務の中核を担い、大量の個人情報をデジタルで扱う機会が増加しているためです。そして、デジタル化の進展に伴い、企業は常にサイバー攻撃や個人報漏洩のリスクに直面しています。
実際には、不正アクセスやマルウェア感染による個人情報の流出、従業員の不適切な個人情報管理など、さまざまな要因で個人情報が流出する事例が頻発しています。とくに近年は、ランサムウェアによる攻撃や標的型メール詐欺など、手口が巧妙化・高度化しており、一度個人情報漏洩が発生すると、損害賠償や信用失墜による経営への打撃は計り知れません。
そのため、企業は技術的対策と人的対策の両面から、包括的な個人情報保護の体制を構築し、継続的に改善・強化する必要があります。
個人情報漏洩が起こる原因
個人情報漏洩の主な原因は、外部からのサイバー攻撃と内部での人的ミスです。サイバー犯罪者による不正アクセスやマルウェア感染が増加し、企業のセキュリティ対策を脅かしています。外部からの攻撃では、フィッシング詐欺が代表的な手法です。巧妙に偽装されたメールやWEBサイトを介して、企業の従業員から個人情報やアカウント認証情報を搾取します。
一方、社内での不適切な個人情報の管理も重大な漏洩原因です。メールの誤送信、USBメモリの紛失、パスワードの使い回しなど、従業員の意図しない操作やセキュリティ意識の低さが情報流出につながっています。個人情報漏洩は、外部からの攻撃と内部での人的要因が複雑に絡み合って発生するため、総合的な対策が求められます。
個人情報の漏洩を防ぐための8つの対策


個人情報保護を学ぶ個人情報保護士
企業の個人情報漏洩対策は、ひとつの対策だけでは不十分です。外部からのサイバー攻撃や内部での人的ミスなど、多様な脅威に対して包括的な対策が求められています。ここでは、企業が実践すべき8つの対策を紹介します。
メールの誤送信対策を行う
メール送信時の二重チェック体制は、個人情報漏洩を防ぐための重要な対策です。企業の個人情報漏洩事故の多くは、メールの誤送信が原因で発生しているためです。具体的には、宛先の確認機能やメール送信前の承認プロセスを導入し、メール本文や添付ファイルに機密情報が含まれていないかを確認する仕組みを整備します。
また、BCC機能の使用を徹底し、複数の宛先に送信する際はとくに慎重に確認しなければなりません。大手企業では、メール誤送信防止ツールを導入し、送信前の自動チェックや一定時間の送信保留機能を活用して、ヒューマンエラーを最小限に抑えています。メール送信時の確認体制を整備し、すべての従業員が確実に実行することで、個人情報の漏洩リスクを大幅に低減できます。
情報機器の持ち出しを制限する
企業の情報セキュリティ対策として、PCやUSBメモリなどの情報機器の社外持ち出しに関する厳格なルール設定が必要不可欠です。情報機器の紛失や盗難は、重大な個人情報漏洩事故につながる危険性が高いからです。対策の具体例としては、持ち出し申請システムの導入、承認フローの整備があげられます。
また、持ち出しを許可する機器には暗号化やリモートワイプ機能を実装し、紛失時のデータ保護対策を講じます。さらに、クラウドストレージの活用により、物理的な情報機器の持ち出しを最小限に抑える工夫も効果的です。なお、多くの先進企業ではモバイルデバイス管理(MDM)システムを導入し、社外での情報機器の利用状況を一元管理しています。
このように、情報機器の持ち出し制限と適切な管理体制により、個人情報の社外流出リスクを効果的に防止します。
個人情報が記載されているデータを安易に削除しない
個人情報を含むデータの削除には、適切な手順と承認プロセスが必須です。安易なデータ削除は、重要な情報の喪失や法的問題を引き起こす危険性が高いためです。多くの企業では、重要データの削除には複数の承認者による確認を必要とし、削除履歴を詳細に記録しています。
また、データの重要度に応じて、完全消去ソフトウェアの使用や物理的な破壊など、適切な削除方法を選択します。個人データ削除の厳格な管理体制を整備し、個人データの適切な取り扱いの徹底が重要です。
IDパスワードの管理を徹底する
強固なパスワードポリシーの導入と定期的な更新は、情報セキュリティの基本です。IDやパスワードの不適切な管理は、不正アクセスや個人情報漏洩の原因となるためです。企業では、パスワードの最低文字数設定、英数字記号の混在要求、定期的な変更強制などの基準を設けています。
さらに、二要素認証の導入やパスワード管理ツールの活用により、セキュリティレベルを向上させています。とくに重要なシステムへのアクセスには、生体認証やワンタイムパスワードなど、追加の認証手段を組み合わせるのも一般的です。適切なID・パスワード管理により、不正アクセスのリスクを大幅に軽減し、情報資産を保護します。
セキュリティ対策ツールを導入する
最新のセキュリティ対策ツールの導入は、個人情報漏洩を防ぐうえで重要な対策です。サイバー攻撃は日々進化しており、従来の対策だけでは防ぎきれないためです。具体的には、ファイアウォール、アンチウイルスソフト、不正アクセス検知システム(IDS/IPS)などの基本的なセキュリティツールなどの導入があげられます。
また、近年ではAI技術を活用した高度な脅威検知システムやエンドポイント保護ソリューションの導入も有効な手段のひとつです。多くの企業では、これらのツールを組み合わせた統合セキュリティプラットフォームを採用し、24時間365日の監視体制を構築しています。
適切なセキュリティツールの選定と運用により、外部からの攻撃や内部からの個人情報の漏洩リスクを最小限に抑えます。
ソフトウェアのアップデートを実施する
定期的なソフトウェアアップデートの実施は、情報セキュリティ対策の基本です。既知の脆弱性を放置すると、マルウェア感染や不正アクセスの侵入口として悪用される危険性が高まるためです。企業では、OSやアプリケーションの自動アップデート機能を活用し、セキュリティパッチを迅速に適用しています。
とくに重要なビジネスシステムについては、検証環境でアップデートの影響を確認したうえで、計画的に更新作業を実施します。また、サポート期間が終了したソフトウェアの特定と更新計画の策定も重要な取り組みのひとつです。継続的なソフトウェアアップデートにより、既知の脆弱性を解消し、システムの安全性を維持します。
信頼性の低いWEBサイトやメールはアクセスしない
不審なWEBサイトやメールへのアクセスの制限は、個人情報漏洩対策の重要な要素です。悪意のあるWEBサイトやフィッシングメールは、マルウェア感染や個人情報の窃取を引き起こす主要な経路だからです。企業の多くは、WEBフィルタリングシステムを導入し、危険なサイトへのアクセスをブロックしています。
また、メールセキュリティゲートウェイを活用して、フィッシングメールや不審な添付ファイルを自動的に検知・隔離しています。さらに、URLリンクの事前スキャン機能により、メール本文中の悪意のあるリンクを無効化する対策も採用されているのがほとんどです。アクセス制限と技術的対策の組み合わせにより、外部からの脅威による個人情報の漏洩リスクを効果的に防止します。
社内で個人情報漏洩に関する研修を実施する
定期的な情報セキュリティ研修の実施は、組織全体の個人情報保護の意識を高める基盤といえます。最新のセキュリティ対策も、すべての従業員の意識と行動が伴わなければ、その効果を十分に発揮できないためです。研修プログラムでは、実際の事例を用いたケーススタディや模擬フィッシングメールによる訓練を実施します。
また、情報の取り扱いに関する社内規定の周知徹底、インシデント発生時の対応手順の確認もおこないます。とくに新入社員や役職者には、それぞれの立場に応じた専門的な教育を提供し、組織全体のセキュリティレベルを向上させなければなりません。継続的な教育と訓練により、従業員の情報セキュリティ意識を高め、人的要因による個人情報漏洩を防止します。
個人情報漏洩対策には総合的な対策も重要
日々進化するサイバー攻撃や、複雑化する情報システムから「個人情報」を守るには、多角的なアプローチが欠かせません。ここでは、先述した8つの個人情報漏洩対策以外の具体策を紹介します。
操作ログの管理
システム操作ログの厳格な管理は、個人情報漏洩の早期発見と防止に重要な役割を果たします。従業員による不正アクセスや個人情報の不適切な取り扱いは、内部からの個人情報漏洩の主要な原因だからです。企業では、ログ管理システムを導入し、誰がいつどのような情報にアクセスしたかを記録・分析しています。
通常とは異なる時間帯のアクセス、大量のデータダウンロードなど、不審な操作パターンを検知した場合には、即座にアラートを発信し、セキュリティ担当者が調査を開始します。操作ログの適切な管理と監視により、内部不正の抑止効果を高め、万が一の事故発生時には原因究明と被害の最小化に役立てるでしょう。
多層防御
複数のセキュリティ対策を組み合わせた多層防御は、個人情報漏洩を防ぐ効果的な方法です。単一の対策では、高度なサイバー攻撃に対して十分な防御力を発揮できないからです。企業の多くは、ネットワーク境界での防御、エンドポイントでの保護、データ暗号化など、異なる層での対策を実施しています。
外部からの攻撃に対してはファイアウォールとIPS、内部での個人情報漏洩に対してはアクセス制御とデータ暗号化、人的ミスに対しては研修と運用ルールを組み合わせて対策を講じるのが通常です。多層防御の採用により、ひとつの防御が突破されても他層で攻撃を阻止し、個人情報の漏洩リスクを最小限に抑えられます。
セキュリティホール対策
システムの脆弱性を継続的に特定し修正するセキュリティホール対策は、個人情報漏洩を防ぐ重要な取り組みです。サイバー攻撃の多くは、既知の脆弱性を悪用して個人情報への不正アクセスを試みるためです。具体的には、脆弱性スキャナーを用いた定期的な診断、セキュリティ情報配信サービスの活用により、システムの弱点を早期に発見します。
また、発見された脆弱性に対しては、影響度と緊急度を評価したうえで、優先順位をつけて修正パッチの適用や設定変更するとよいでしょう。計画的なセキュリティホール対策により、システムの安全性を維持し、外部からの攻撃による個人情報漏洩を防止します。
まとめ
本記事では、企業における個人情報漏洩対策について解説しました。個人情報の漏洩は企業の信用を大きく損なう重大な問題であり、技術的対策と人的対策の両面からの包括的な取り組みが不可欠です。デジタル化が進むなかで、個人情報の取り扱いや保管方法には、より慎重な対応や施策が求められています。

個人情報保護を学ぶ個人情報保護士